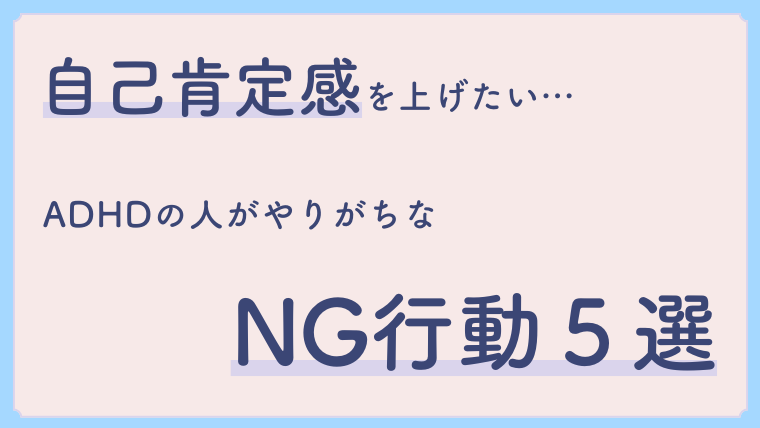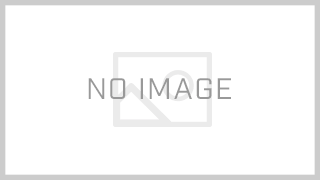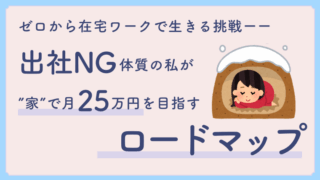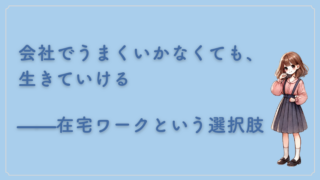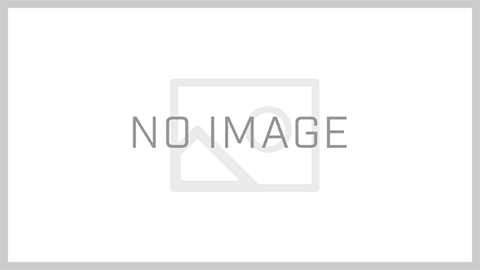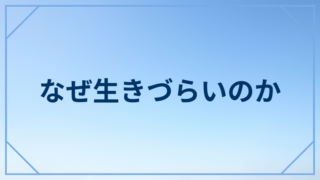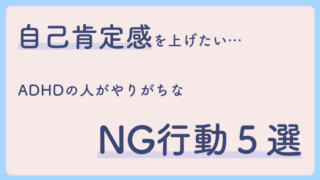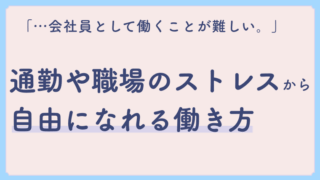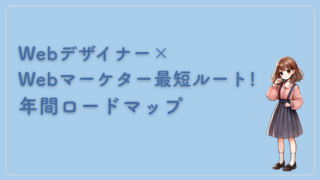◆
◆
◆

毎日生きるためにやることはたくさんある。
朝はバタバタと出勤準備、仕事中はミスしないよう神経をすり減らし、帰宅すれば買い物・家事・疲れた体。
毎日こなすだけで精一杯。
だけど、私たち「発達障害」や「ADHD」の傾向がある大人にとっては、それだけでは終わりません。
たとえば──
朝早く起きて支度して、時間にも余裕を持って家を出たのに、途中で寄り道してしまって遅刻。
「どうしてまた…?」と上司にため息まじりに怒られた。
やっと覚えたと思った仕事も、うっかりメモをなくしてもう一度質問。
「この前も言ったよね?」の言葉に、喉の奥がキュッと苦しくなる。
周りの同僚はどんどん仕事を覚えて評価されていくのに、
私はミスばかりで、自信も自己肯定感も、日々ちょっとずつ削られていく。
そんなふうに自分を責めてばかりで、気づけば心も体もすり減っている。
それでもなんとかしたくて、「ADHD 自己肯定感」「発達障害 自信 取り戻す」なんて言葉を検索して、
「自己肯定感を高める習慣」や「ポジティブ日記」「目標設定」みたいな方法を頑張って試してみる。
けれど──続かない。できない。そしてまた、自己嫌悪のループに陥る。
もし、あなたもそんなふうに「よくある解決法」を試してみて、
うまくいかなかったことに自分を責めてしまっているなら、大丈夫です。あなたのせいじゃありません。
あなたに合っていない方法で、真面目にがんばってきただけなんです。
この記事では、
まず「ADHDの人はなぜ自己肯定感を下げやすいのか」という前提をお伝えした後、「よくある自己肯定感アップ法」が当てはまらない理由を解説します。
そして後半では、
✔ ADHDの人がやりがちな「間違った自己肯定感アップ法」
✔ それに代わる、“続かなくても自己否定しない”やさしい考え方
をご紹介します。
「ここはもう知ってるよ」というところがあれば、もちろん読み飛ばしても大丈夫です。
あなたがあなたのままで、少しでも心が軽くなるヒントが見つかりますように。
◆
◆
◆
なぜADHDの人は自己肯定感が下がりやすいのか?
自己肯定感が低い──そう自覚した時、
「私ってなんでこうなんだろう?」「なんでこんなに自信がないの?」と思ったことはありませんか?
でもそれは、あなたの性格が悪いわけでも、努力が足りないからでもありません。
たとえば、小さな頃から…
・忘れ物が多くて、いつも先生や親に叱られていた
・落ち着きがないって言われて、輪の中に入りにくかった
・みんなと同じペースで勉強や作業ができず、浮いてしまった
・空気を読むのが難しくて、人間関係がギクシャクしやすかった

そんな「できなかったこと」や「迷惑をかけた」と思わされる経験が、積み重なっていませんか?
このように、ADHDの傾向がある人は、もともと「できないこと」にフォーカスされやすい環境で育ってきた人が多くいます。
さらに大人になってからも、会社や社会の中で…
・うっかりミスや確認漏れで信頼を失う
・指示通り動けない自分を責めてしまう
・周りは要領よくこなしているのに、自分だけ取り残されている気がする
そうした体験が繰り返されることで、
「私ってダメなんだ」
「どうせ何をやってもうまくいかない」
という思い込みが、心の奥深くにこびりついていくんです。
これは、自分に対する信頼や価値を少しずつ削っていく、静かな自己否定の積み重ね。
つまり、自己肯定感が低いというよりは、“削られ続けてきた”という方が正しいのかもしれません。
なぜ「よくある自己肯定感アップ法」がADHDの人には逆効果なのか?
「このままじゃいけない」と思ったあなたは、
ネットや本、SNSでいろんな“自己肯定感を高める方法”を調べたはずです。
・ポジティブな日記を書く
・目標を立てて、達成して自信をつける
・毎朝早起きして、自分を整える
・誰かと比較することをやめて、“自分の人生”に集中する
どれも正しそうだし、やってみた人も多いと思います。
でも──
うまく続けられなかった。
忘れてしまった。
やってる途中で苦しくなった。
そして、気づけばまた自己否定。
「なんで私はこれすらできないの?」
「やっぱり私は変われないんだ」
それもそのはず。
これらの方法の多くは、定型発達の人(ADHDではない人)向けに設計された“自己管理”が前提のものなんです。
ADHDの特性が“方法そのもの”とぶつかる
でも、ADHDの特性がある人は…
◾️気分や集中力に波がある
◾️見通しを立てたり、計画を維持したりするのが難しい
◾️外部の刺激に反応しやすく、環境に左右されやすい
◾️感情のアップダウンや自己評価の変動が激しい
つまり、「毎日コツコツやる」「続けて積み上げる」といった自己肯定感の育て方は、そもそも“脳の特性”と噛み合っていないことが多いんです。
あなたが続けられなかったのは、意志が弱いからじゃありません。
あなたの真面目さが、“合わないやり方”で自分をさらに苦しめてしまっただけなんです。
このあと紹介する「やりがちなNG行動5つ」では、
そんな“つまずきやすい自己肯定感アップ法”と、
それに代わる「失敗しても自己否定しない」やさしい方法をご紹介していきます。
どうか、「変われなかったのは自分が悪かったから」と責める前に、
“やってみた方法が自分に合っていたかどうか”を見直してみてください。
あなたの心が楽になるヒントがきっと見つかります。
自己肯定感を上げたい人がやりがちなNG行動5つ
①毎日同じルーティンを作ろうとする(でもできない)
「朝7時に起きて、10分だけ掃除して、夜は日記を書いて寝る!」
そんなふうに、自己肯定感を上げるための「理想的な毎日」を設定したことはありませんか?
でも、ADHDの特性を持っていると、「毎日決まったことをやる」のがそもそも苦手。気分や集中力、刺激の受け方にムラがあるからこそ、予定通りにできないことが続きます。
そして結局、
「またできなかった…」「やっぱり私はダメなんだ」
と、自己肯定感を上げるどころか“失敗体験”を重ねてしまうのです。
💡「選択式のゆるルール」に変えるのがポイント。
「できそうなことを3つリストにして、そのうち1つでもできたらOK」くらいの“柔らかさ”が、自己肯定感を削らない鍵です。
全部やらなくても、1つやれたら「私、今日はよくやった」と言ってあげてください。
②ポジティブな日記を毎日書こうとする(でも忘れる)

「今日はよくやった!」「〇〇ができて偉い!」
そんなふうに前向きな日記を書けば、気分が明るくなって、自己肯定感が高まる──
確かに理屈ではそうかもしれません。でも、ADHDの人にとって「毎日やる」「思い出して書く」「文を構成する」という作業は、想像以上にエネルギーを使います。
気づけば三日坊主。
「また続かなかった」という現実が残って、自己否定の材料に…。
💡“書かなくても自己肯定できる仕組み”を使いましょう
たとえば、「今日は洗濯できた!」と思ったら、スマホのメモやLINEの自分宛てトークにポンっと書くだけでOK。
難しく考えず、朝ごはんを食べた、起きられた、どんなことでも1つできたことを“見える化”するだけで、心がちょっと軽くなります。
1行日記や音声メモも、自分を認めるツールになります。
③「人と比べない努力」をしすぎる

「人と比べなければ自己肯定感は上がる」
この言葉、よく見かけますよね。
でも、ADHDの人にとって「比べない努力」は、かえってストレスになりがち。
なぜなら、情報や感情に過敏だから、比較は無意識に起こるものなんです。
そして、比べてしまった自分をまた責めてしまう──
「こんなことにイライラしてる自分がイヤ」「また劣等感持ってる…」
💡「比べてもいい。でも“使い方”を変える」
比べたら、「なんで私はできないの…」と責める代わりに、
「あの人、どうやってやってるんだろう?私にもできる方法あるかな」とちょっとだけ観察モードになってみてください。
自分を責める材料じゃなく、「使えるヒント」だけ取り出す視点があると、比べても疲れにくくなります。
④目標を立てて達成しようとする
「今月こそ家計簿をちゃんとつける!」
「毎朝30分早起きして読書を習慣にする」
「週3でジムに通ってダイエット!」
…こんなふうに、生活を整えたり、自分を変えたりする目標を立てて、
「できたらきっと自己肯定感も上がるはず!」と頑張ろうとしたこと、ありませんか?
けれどADHDの特性があると、
計画通りに動く・ペースを守る・コツコツ続けることに苦手さを感じやすく、
途中でうまくいかなくなることもしばしば。
すると…
「結局、また続かなかった」
「どうして私は“普通のこと”ができないんだろう」
と、自分を責めてしまう結果に。
「できなかった自分」にフォーカスしてしまい、自信をなくしてしまいます。
💡「やったらラッキー」くらいの“ゆる目標”でいいんです。
たとえば「今日は家計簿アプリを開くだけでもOK」にして、できたら思いっきり自分を褒める。
「ジムに行けなかったけど、エレベーターじゃなくて階段使った」など、
行動の“達成率”より“動けた事実”に〇をつけてあげることが大切です。
できたか・できなかったかではなく、
“動こうとした自分”を認めてあげることから、自己肯定感はじんわり育ちます。
どんなに小さな一歩でも「行動できた事実」を積み重ねることが、結果的に大きな自信になります。
⑤「自分を好きになる言葉」を言い聞かせる
「私はできる」「私には価値がある」
…頭ではわかってる。でも、なぜか心に届かない。
実は、ADHD傾向がある人は、現実とつながっていない言葉を受け入れるのが苦手です。
「嘘っぽく感じる」「そんなわけない」と、むしろ逆効果になることも。
💡事実ベースの「できたこと」を拾うこと。
「今日、買い物に行けた」「メールを返せた」「ベッドから起きられた」
それだけで、“自分を認める根拠”になります。
言葉よりも、“行動と結果”に注目することで、信じられる自己肯定感が育っていきます。
以上が、ADHDの人がついやってしまいがちな「自己肯定感を下げてしまう行動5つ」と、代わりに取り入れてほしい工夫です。
ADHDのあなたに合った「やさしい自己肯定感の育て方」
続けられなくていい。「単発の行動」に〇をつけよう
「毎日やらなきゃ意味がない」と思っていませんか?
でも、ADHDの人にとっては「継続」よりも「その日できたこと」に目を向ける方がずっと効果的です。
むしろ、“続かなくてもいい”と最初から決めておいたほうが、
プレッシャーが減り、行動のハードルが下がります。
たとえば、
◎「スマホを見ずに5分間だけ集中できた」
◎「カフェに行けた自分、えらい」
◎「今日は洗濯物を干せた!すごい」
…1回でもできたら、それは100点満点でいいんです。
自己肯定感は「高める」よりも「減らさない」が大事
ADHDの人は、気づかないうちに自己肯定感が削られるシーンに多く遭遇します。
・注意されたときに「また迷惑かけた」と自責する
・SNSを見て「みんなできてるのに」と比較して落ち込む
・「またできなかった」と自分にダメ出し

このように、「上げる」より前に、「これ以上減らさない」ことが実はとても大切なんです。
おすすめは…
◎「できなかったこと」にはコメントをしない
◎「疲れてできなかった自分もOK」と言ってあげる
◎ミスをしても「たまたま」「タイミングの問題」と一時停止する癖をつける
自己否定の“自動反応”を少しずつ止めていくだけでも、心の疲れは確実に減っていきます。
自分を“好き”になれなくても、「今の自分でOK」と言ってみる
「自己肯定感=自分を好きになること」
そう思っていませんか?
でも、「自分が好き」とまでは言えなくても、
「今の自分も悪くないかも」
「このままでも、なんとかやれてる」
そう思えたら、それだけで立派な“肯定”です。
大切なのは…
◎「好きにならなきゃ」と無理に前向きになろうとしない
◎「否定しなくていい自分」からスタートすること
◎評価を「好き/嫌い」から「そのままOK」に変える視点
“今のままでスタートできる自己肯定感”を育てていくことが、ADHDの人にはとても合っています。
補足:やさしい肯定感は、「自分を助ける言葉」から始まる
最後に、自分を責めたくなったときに使ってほしい言葉をひとつ。
「それでも、今日の自分はちゃんと生きてたよ。」
言い訳でも甘えでもなく、これは生き延びてきた自分への敬意です。
まずはそこから、やさしい自己肯定感を育てていきましょう。
まとめ|間違った方法をやめれば、自己否定ループから抜け出せる
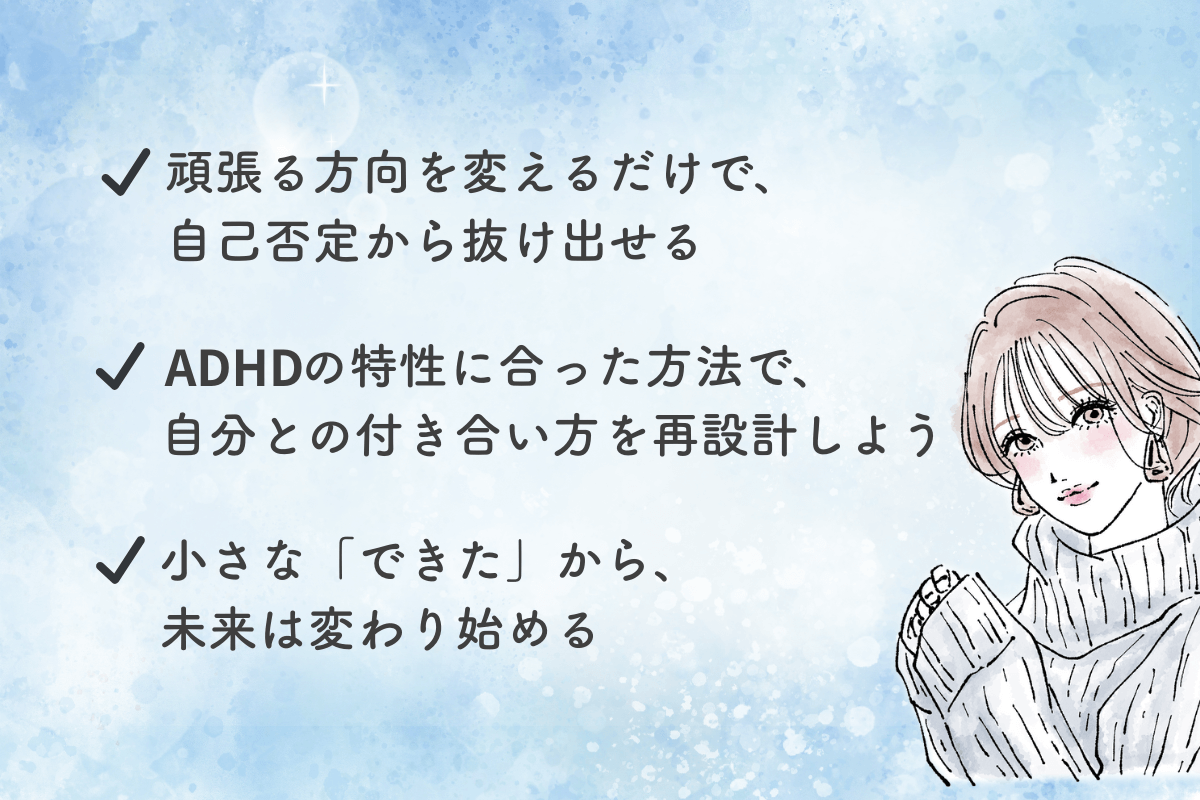
ADHDの傾向があると、自己肯定感はどうしても揺らぎやすいもの。
「失敗を繰り返す自分を責める」「頑張っても続かない」「またできなかった……」
そんなふうに、一生懸命やっているのに自信を失ってしまうこと、たくさんあると思います。
でも、それはあなたの“意志が弱いから”でも“能力が足りないから”でもありません。
むしろ──
「あなたに合わない方法で、自分を変えようとしてきただけ」なんです。
この記事では、ADHDの人がやりがちなNG行動と、その代わりに取り入れてほしい「やさしい自己肯定感の育て方」をご紹介しました。
もう一度、要点を振り返っておきましょう。
❗️ADHDの人がやりがちなNG行動
・ルーティンを決めて縛ってしまう
・毎日ポジティブ日記を書こうとする
・「人と比べない」ことにエネルギーを使いすぎる
・高い目標を立てては未達で落ち込む
・自分を好きになる言葉を無理に信じようとする
🍀 代わりに取り入れてほしい「やさしい育て方」
◎単発でもできたことに〇をつける
◎自己肯定感を「高める」より「減らさない」
◎自分を好きになれなくても「このままでもいい」と思える視点
誰かの成功体験や理想の習慣をマネしてうまくいかなくても、大丈夫。
あなたには、あなたに合ったやり方があります。
大切なのは、「自己肯定感を育てること」によって、
あなたが毎日、自分をちょっとだけ許せるようになること。
そして、何よりも忘れないでほしいのは──
あなたは、今日までよく頑張ってきた。
続かなくても、揺らいでも、それでも生きてる。
それはもう、十分に誇れることなんです。
ここまで読んでくれて、本当にありがとうございます。
この記事が、あなた自身を少しやさしく見つめ直すきっかけになれたら嬉しいです。